
大阪大学卒/塾講師歴5年/家庭教師歴6年/E判定から阪大へ逆転合格/勉強法を教えた生徒は「2週間で苦手教科が27→73点」「定期テストの5教科合計200点以上アップ」「E判定から3ヶ月で逆転合格」など、劇的な成績アップを多数達成/著書『成績があがる中学生の勉強法』『だから勉強ができない20の考え方』

やらなきゃいけないとわかっているのに、どうしても勉強が続かない



子どもの勉強がいつも「三日坊主」で終わってしまう…



こんな悩みにお答えします!
そんな経験はありませんか?
実はこれ、やる気や根性だけではどうにもならない場合が多いのです。人間の脳は、“楽なほう”や“楽しいほう”に流れがちなので、意志の力だけで勉強を継続するのはめちゃくちゃ難しいことなんです。
しかし、一度「習慣化」されると、「モチベーション」や「やる気」に左右されずに”自動的に勉強を続けられる”ようになります。
たとえば「寝る前の歯磨き」が良い例です。私たちはやる気満々なモチベーションで毎回歯磨きをしているわけではありません。
「やる気があろうとなかろうと、歯磨きしないと落ち着かない…」となっていませんか? これが「習慣化」の力です。同じことを勉強で起こせたら、これほど強力なことはありませんよね。
本記事では、私が長年の指導のなかで実際に試し、“これは効く”と確信を得た8つの習慣化のコツを厳選して解説します。



目標達成のために、ぜひ真似してみてください!


「よし、今日から毎日3時間やるぞ!」。これは習慣化に挫折する「よくある失敗」です。
勉強を習慣化できていない状態で「毎日3時間やろう!」と意気込んでも、大半は続きません。どうしても精神力に頼りきりで、「今日はやる気が出ないから…」となればすぐに中断しがちです。
さらに、3時間のまとまった時間を本当に確保しようとすると、他のスケジュールや遊びの時間を思い切り削らなければならず、「しんどい」「疲れる」と感じてしまいがち。その結果、“もう無理”と投げ出してしまうことが多いのです。
そこでおすすめしたいのが「最初のハードルを極限まで下げる」作戦です。
とにかく何でもいいので、勉強を一歩だけ進めること。「5分だけ問題を解いてみる」「ワークを1ページだけ開いてみる」といった形でOK。
何より大切なのは、“机に向かうまでのハードル”を低く設定すること。「少しだけやる」なら、脳の抵抗感もグッと下がり、「それならやってもいいかも」と思えるようになります。






また、心理学では「スモールステップ」という概念があります。大きな目標をいきなり狙うのではなく、小さな成功体験を積むことで自己効力感が高まり、長期的な継続を実現しやすくなる。まさに、最初の5分が自信アップのカギになるのです。


勉強を習慣化するためには、「何時にやるのか」を決めておくことが効果的です。
人間は、曖昧な計画を立てると“先延ばし”をしがちです。「やらなきゃなー」と考えていても、「後でいいか」「もう少し休憩してから…」という具合に、どんどんずれ込んで結局できないことは「勉強あるある」です。でも、勉強できる人はこれを「あるある」にしません。
先延ばしを撃退するために有効なのが、「19時〜20時は英語」「20時〜21時は数学」など、時間をブロックで区切ってしまう方法です。
時間を先に決めてしまえば、その時間になれば“やらないと逆に落ち着かない”という心理状態になりやすい。いわば、外部から自分に“締め切り”を課しているようなものです。






さらに踏み込むなら、「19時からはこの参考書の◯ページ~◯ページ」と「その時間に何をやるのか」まで決めるのが理想です。
勉強に取りかかる際に「さて、何をやろう…」と迷う時間があると、その迷い自体がストレスになり、“もういいや”となるケースが少なくありません。



「勉強しようと思ったけど、今日はやらなくてもいける気がする」と思ったことはありませんか?
「時間+内容」で二重にスケジューリングを固めておくことで、取りかかりもスムーズに計画倒れを防げるようになります。


「何をしたら勉強をするのか」を決めることでも、勉強は習慣化できるようになります。
私たちの普段の行動は、「〇〇をしたら△△をする」という形で連鎖しています。たとえば歯磨きは、“食事が終わったら”とか“お風呂から上がったら”など、特定の行動の後に行う人が多いでしょう。
この“行動の連鎖”を利用して、「夕飯後の片づけが終わったら英語を始める」「お風呂に入ったら、その後数学のワークを開く」というように、習慣に組み込みたい行動を他の行動の後にセットすると習慣化ができます。






これは心理学的に「実行意図(Implementation Intention)」や「if-Thenプランニング」と呼ばれる方法です。
“○○の状況になったら△△をする”と具体的に決めると、脳が先読みをして行動を“自動化”しやすくなります。
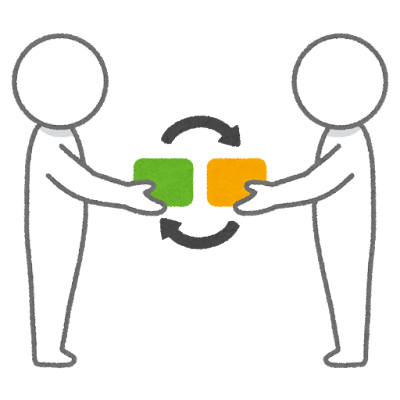
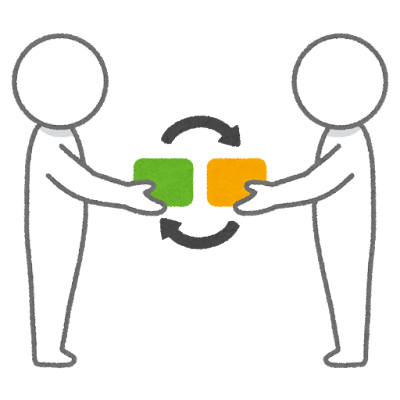
勉強を習慣化できる人は「勉強時間の代わりに何を辞める(減らす)のか」をきちんと考えています。
時間には限りがあります。1日24時間は誰にとっても変わりません。だからこそ、勉強時間を増やす=他の何かに使っていた時間を削るということです。
「勉強時間を増やしたい!」と思ったら、同時に「では今までやっていた◯◯の時間を減らそう」という決断が必要です。
ここで大事なのは、何かを“全部やめる”のではなく、「優先順位をもう一度見直してみる」ということ。ゲームが楽しみなら、完全にやめる必要はありませんが、1時間やっているところを30分にするだけでも良い。






一番おすすめなのは「スマホをだらだら見る時間を辞める」です。やりたくてやっているわけではなく、なんとなくSNSやゲームなどをしてしまっていた時間が誰にでもあるはずです。この時間を削ることができれば、勉強時間はめちゃくちゃ増えます。
“優先度が低いもの”を削るという考え方をベースに、どの時間を削れるのか?を考えてみてください。好きなことを諦めなくても、意外と大きな時間を捻出できます。
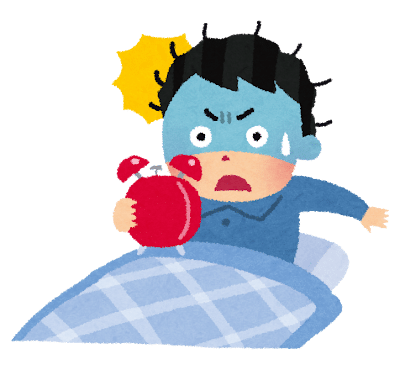
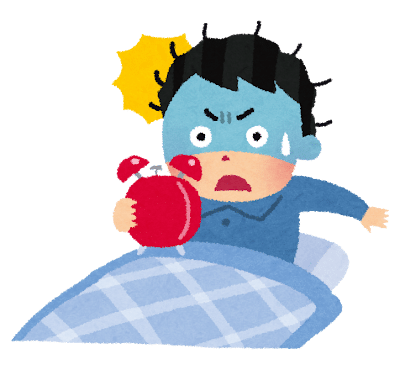
せっかく習慣化できてきても、三日坊主になってしまう。これを防ぐために「アラームを活用すること」がおすすめです。
人間の脳は面白いもので、「今やりたいこと」や「楽なこと」を優先するようにできています。ちょっと疲れていたらすぐソファーに横になりたくなるし、面白い動画を見つけたらつい観続けてしまう。
そんなときに効果を発揮するのが「アラーム」です。アラームは強制的に思い出させてくれる“外部のリマインド役”です。たとえば、「19時に英語スタート」を決めておいて、その数分前にもアラームを設定しておく。鳴ったら「よし、始めるか」とスイッチを入れられます。






勉強に限らず、起床時間、就寝時間、移動時間など、アラームがルーティンを確立する助けになるのはどの年齢でも共通しています。
「火曜日19時には数学をやる」とスケジュールで決めたなら、アラームアプリを活用して「繰り返しアラーム」として毎週火曜日の19時にアラームがなるように設定するのがおすすめです。(アプリはなんでもOKです)
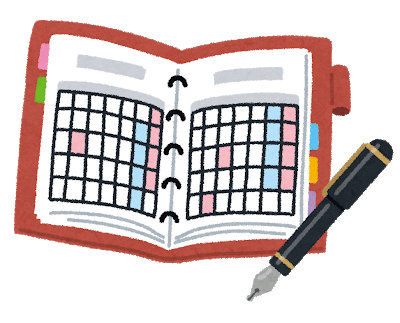
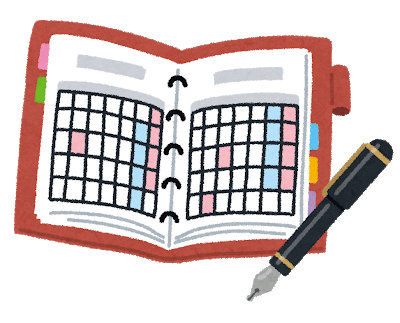
完全に習慣化するまでは「朝イチでスケジュールをチェックすること」を意識すると、挫折がしにくくなります。
勉強の予定を立てていても、結局「今日は何をするんだっけ?」と忘れてしまいがち。部活や学校行事、友達との予定などが入ると、簡単に頭から抜け落ちます。
これを防ぐには、朝起きてから(または朝食後)にその日のスケジュールを確認する習慣を作りましょう。あれこれ忙しい中でも「今日は19時からワークを2ページ、20時から英単語暗記」と思い出しておけば、一日の全体像がはっきりして気分も楽になります。






朝に立てた計画が実行できなかったとしても、次の日に再チャレンジすればOKです。まずはハードルを下げて、続けてみてください。“朝チェック”の習慣自体も、徐々に「習慣化する力」の積み重ねを助けてくれます。
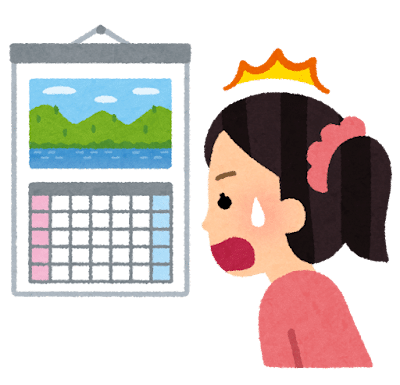
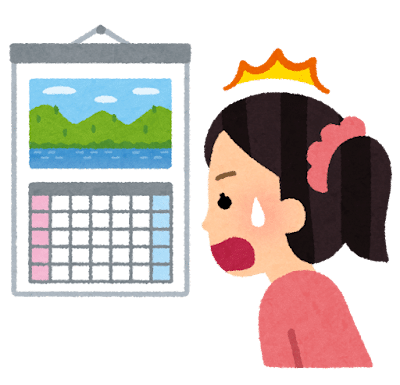
スケジュールは毎朝見るだけでなく、「見えるところに貼っておくこと」もおすすめです。
人はとにかく忘れる生き物です。とくに中学生は部活や友達とのやり取り、趣味など、頭を使う場面が多い。せっかく考えた計画も、翌日には忘れてしまうことがあります。
だからこそ、物理的な“見える化”が重要。家の中で頻繁に目に入る場所、たとえば
などに、手書きのスケジュール表や「今日やることリスト」を貼っておきましょう。ちょっと恥ずかしいと思うかもしれませんが、効果は抜群です。








スマホはLINEやSNS、動画、ゲームなど誘惑も多いですが、逆に“勉強のためのリマインダー”として活用するのも賢い方法です。
たとえば、スマホのホーム画面を「今日のスケジュール(19時〜英語2ページ、20時〜数学ワーク)」「今週の目標(英単語60個覚える)」などのメモ画像にしておく。あるいは付箋アプリやリマインダー機能を使って、ホーム画面に常に表示するウィジェットを置く。そうすれば、スマホを開くたびに自然と「そうだった、今日は英語やらなきゃ」と思い出せます。






習慣化で大事なのは、「自分を信じすぎない」ことです。どういうことかというと、人間は意志やモチベーションを過大評価しがちで、「自分ならやれるはず」と思い込みます。しかし実際は、環境の影響を強く受け、少し疲れただけで「明日やればいいや」と先送りしてしまったり、誘惑に負けてしまったりするのが現実です。
だからこそ、自分の意志に頼らなくても勝手に実行されるような“仕組み作り”が必要になります。本記事で紹介したコツこそが、「仕組み」で自分をサポートする作戦の具体例です。
改めて、習慣化の8つのコツをまとめます。
これらの仕組みをできるだけ同時並行で導入してみると、勉強が「やろうかどうしようか迷うもの」から「やらないと落ち着かないもの」「やっているのが当たり前なこと」に変わっていきます。
大切なのは、“自分の意志”ではなく“仕組み”で続けられる環境を作ること。最初は少し面倒だと感じるかもしれませんが、一度波に乗ってしまえば、今まで以上にラクに勉強を続けられる自分に出会えるはずです。



一つだけでも実践すれば効果はありますが、複数の方法を組み合わせると相乗効果が生まれて、勉強習慣が一気に「当たり前」になっていきます。ぜひ試してみてください!
ここまで読んでくださった方は、ぜひ今すぐ行動に移してみてください。
「なるほど。参考になった。」では、まだ未来は変わりません。行動に移して、はじめて成績アップが実現します。
ほんの小さなアクションでも、やり始めれば「意外とできるかも」と気づき、自己効力感(やればできる自信)もどんどん高まっていきます。
そうすれば、「勉強ができる人のマインドセット」もどんどん養われていって、加速的に成績が上がるようになります。









がんばっているのに、子どもの点数があがらない…



やり方が間違っているだけです。
「正しい勉強法」でやれば、短期間でも面白いほど上がります!
お子様の成績が上がらない原因は頭が悪いわけでも、才能がないわけでもありません。
「間違った勉強法」で勉強をしてしまってるだけです。
私が塾講師や家庭教師として「正しい勉強法」を教えた生徒たちは、次のような圧倒的な成績アップができました。
みんな「勉強が苦手…」と悩んでいた生徒でした。でもその原因は「間違った勉強法でやっていただけ」なんです。
勉強は才能ではなく、やり方で劇的に変わるんです。
実は、この勉強法は今すぐご家庭でも真似することができる方法です。でも、多くの子どもたちは間違った勉強法で努力してしまっています。この方法を知らずに、「勉強が苦手」と悩みながら頑張るのは、とてももったいないことだと思っています。
だから、「お子様の成績アップを願う保護者の皆さま」のために、「正しい勉強法」を徹底解説する無料の勉強法講座を開講しています。
LINEで、私が塾でも教えていた勉強法を出し惜しみなく解説したLINE限定の無料7日間講座をお送りしています!
これまで5000名以上の保護者さま、1000名以上の生徒さんに参加いただいて、「過去最高点だった!」「五教科で100点もあがった!」という成績変化のお声もたくさんいただいています。


勉強ができないのは才能の問題ではありません。ただ、「正しい勉強法」を知らないだけなんです。
私は確信を持って、そう言えます。
なぜなら、私自身がそれを身をもって経験してきたからです。
勉強が伸び悩むのは才能ではなく、やり方が間違っているだけです。
でも、テクニック的に勉強して、テストの点数や合格だけとっても、将来に役に立ちません。
でも、本質的な考えに基づいて勉強すれば、テストも劇的に伸び、将来にも応用が効きます。
正しく勉強できれば、成績は伸び、受験も合格でき、何よりも将来に活きるんです。
逆に、正しく勉強できなければ、がんばっても結果が出ず、「才能がない」と思い込んでしまいます。
勉強は才能ではなく、やり方の問題です。正しくやれば、誰でも面白いほど伸びます。
無料講座では「正しい勉強法」について、体系的に深くまでご紹介しています。お子様の成績アップのために、ぜひご活用ください。
今なら、登録いただいた方へ
を無料プレゼント中です!
多くの生徒の成績を上げたノウハウがギュッと凝縮されているマニュアルのため、ぜひお受け取りください!