
大阪大学卒/塾講師歴5年/家庭教師歴6年/E判定から阪大へ逆転合格/勉強法を教えた生徒は「2週間で苦手教科が27→73点」「定期テストの5教科合計200点以上アップ」「E判定から3ヶ月で逆転合格」など、劇的な成績アップを多数達成/著書『成績があがる中学生の勉強法』『だから勉強ができない20の考え方』




このような「勉強時間を確保しようとすると、別の作業(部屋の片付けなど)をはじめてしまう」というケースは珍しくありません。実は「やる気を出しているように見えるのに、肝心の勉強ではない作業にのめり込んでしまう」現象は、心理学的にもしばしば説明されるものです。
本記事では、この“テスト勉強のはずが部屋の片付けを始めてしまう”という悩みを解決するために、まずは心理的な要因から考察し、そのうえで具体的な勉強法や生活習慣の改善につなげる方法を解説していきます。


勉強は“先の結果がすぐに見えにくい”作業です。
たとえば部屋の片付けであれば、掃除をすれば目に見えて「きれいになった」という達成感や満足感を即座に得られます。
しかし、勉強の場合は学習の成果が試験本番までわかりにくく、さらに頭を使う・覚えるという負荷がかかるため、無意識に避けたい気持ちが働きやすいのです。



「勉強をして良い点数を取らなければいけない」というプレッシャーが大きいと、その重圧から“まだ自分は本気を出していない”状態を維持しようとする場合があります。
もし本気を出して勉強しても成績が上がらなかったらどうしよう…という不安や恐怖が背景にあることも多いです。
そんなとき、人は“本気でやっていないから結果は仕方ない”と思いたがる心のクセが働きます。そこで、部屋の掃除や他の作業を優先することで、無意識に逃げ道を確保してしまうのです。



人間は「周りのみんながやっていること」や「自分の慣れ親しんだ習慣」に流されやすい生き物です。
たとえば、「やらなきゃいけない勉強」があるときに、部屋の片付けやスマホチェックなど“勉強以外の行動”でスタートしてしまうのは、実は周囲でも同じ行動をとる仲間が多いからかもしれません。
「自分だけじゃないし、みんなもやってるし」という安心感が“本筋の勉強に向かわない”現状を後押ししてしまうのです。
しかしながら、テストで良い点数を取りたい、あるいは受験を成功させたいのであれば、“普通の行動”だけを繰り返していたのでは、思うように結果が出せないことが多いのも事実です。


このままでは「片付けを頑張っているからなんとなく充実感はあるけど、テスト勉強は進まない…」という悪循環にはまる可能性があります。
そこで、上記の心理的要因を踏まえた、具体的な解決策を紹介します。
人は「結果がすぐ目に見える」ことに満足感を抱きやすいものです。
勉強がうまく進まないのは、「試験が先で成果がわかりにくい」からという面が大きい。であれば、勉強にも“すぐわかる成果”を設定するとよいでしょう。
単語を10個覚えるごとに確認テストをしてみたり、10分ごとにまとめた内容を自分自身にクイズ形式で答えてみたりする。即座に「できた・できない」がわかるので達成感や悔しさが見えやすくなります。
勉強時間や解いた問題数を“その都度”記録してグラフ化したり、紙にチェックしていくと、「今日はこんなに進んだ」「もう少しで目標に届く」ということが可視化できます。






よく言われる「5分だけやってみよう!」という話は、実は結構理にかなっています。
勉強への心理的抵抗があるときは、“最初の一歩”さえ踏み出してしまえば意外と続くものです。
これは単なる根性論ではなく、行動経済学や心理学でも「イフゼン・プランニング」などの手法として効果が証明されています。
「机に向かう」「筆箱を開ける」「教科書を広げる」など、とにかく小さな行動目標を決め、実行できたら自分をほめる。
スマホが手の届く範囲にあれば、ついSNSチェックやLINEに目がいきがちです。物理的にスマホを別室に置くなどの“スタートの邪魔になるものを排除する”工夫も大切です。






高い目標を持つこと自体は素晴らしいことです。
しかし、それが行動を妨げるほどのプレッシャーになっている場合は、一度ハードルを下げることが大切です。
「まだ完璧じゃなくてもいい。やらないよりはいい」という柔軟な考え方を身につける必要があります。
「完璧に理解するまで終わらない」ではなく、「30分やったら一旦休憩」など、先にゴールを決めておく。
わからない問題があっても、「とりあえず書いてみる」でOKとする。ミスが多くても、“ゼロからまったく手をつけない”よりはるかにマシです。






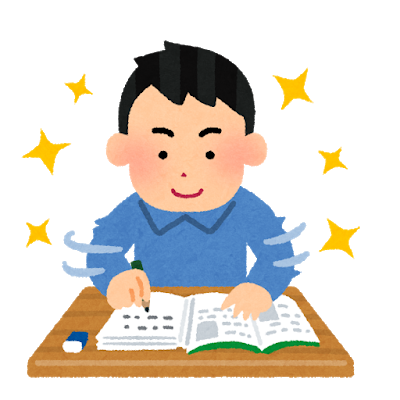
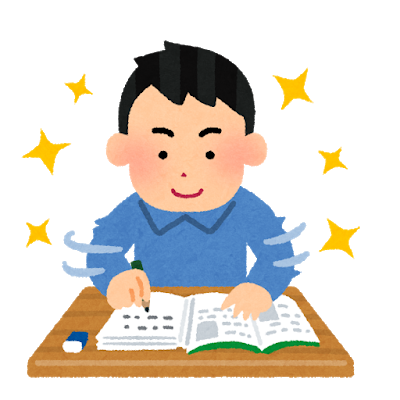
ここまで具体的な対策をいくつか挙げてきましたが、さらに根本的な部分に踏み込んでみましょう。
“自我消耗(Ego Depletion)”という心理学用語があります。
人間の意志力はエネルギーのように限りがあり、睡眠不足や食事の乱れなどで消耗すると、些細な誘惑にも簡単に負けてしまうという理論です。
つまり、しっかり寝て、しっかり食べ、適度な休憩を取るという当たり前のことが、実は勉強のやる気を左右する大きな鍵なのです。
テスト勉強をする理由は、学校の成績を上げるため、志望校に合格するため、など人によってさまざまです。
しかし、その理由が「親や先生に言われたから」ではモチベーションに火がつきにくい。
「英語の成績を上げたい。なぜなら将来英語を使って○○がしたいから」というように、自分の将来の夢や興味と結びつける。
一番苦手な科目にいきなり挑むと挫折しやすい。まずは比較的やりやすい科目から始めてエンジンをかけると、勢いがつきやすいです。






「みんなと同じ行動」をしていたら、テストや受験で“みんな以上”の結果を出すのは難しくなります。
一方で、多くの人がつまずくポイント(今回で言えば「つい片付けを始めてしまって勉強できない」)をいち早く克服できれば、成績が上がる余地は大きいのです。
勉強しようと思った瞬間に別作業をしてしまう人はたくさんいます。
そこをこらえて、逆に“さっと勉強に向かう”習慣を身につけられれば、それだけでライバルよりも先に進むチャンスになります。






部屋の片付けをしてしまう原因は「サボりたいから」だけではなく、心理的抵抗や達成感を得やすい行動への自然な流れ、完璧主義の裏返しなど、さまざまな要因が絡み合っています。
しかし、いずれも対策が可能です。
大切なのは、自分の弱点を否定するのではなく、うまく利用して勉強を継続できる環境や習慣を作ることです。









がんばっているのに、子どもの点数があがらない…



やり方が間違っているだけです。
「正しい勉強法」でやれば、短期間でも面白いほど上がります!
お子様の成績が上がらない原因は頭が悪いわけでも、才能がないわけでもありません。
「間違った勉強法」で勉強をしてしまってるだけです。
私が塾講師や家庭教師として「正しい勉強法」を教えた生徒たちは、次のような圧倒的な成績アップができました。
みんな「勉強が苦手…」と悩んでいた生徒でした。でもその原因は「間違った勉強法でやっていただけ」なんです。
勉強は才能ではなく、やり方で劇的に変わるんです。
実は、この勉強法は今すぐご家庭でも真似することができる方法です。でも、多くの子どもたちは間違った勉強法で努力してしまっています。この方法を知らずに、「勉強が苦手」と悩みながら頑張るのは、とてももったいないことだと思っています。
だから、「お子様の成績アップを願う保護者の皆さま」のために、「正しい勉強法」を徹底解説する無料の勉強法講座を開講しています。
LINEで、私が塾でも教えていた勉強法を出し惜しみなく解説したLINE限定の無料7日間講座をお送りしています!
これまで5000名以上の保護者さま、1000名以上の生徒さんに参加いただいて、「過去最高点だった!」「五教科で100点もあがった!」という成績変化のお声もたくさんいただいています。


勉強ができないのは才能の問題ではありません。ただ、「正しい勉強法」を知らないだけなんです。
私は確信を持って、そう言えます。
なぜなら、私自身がそれを身をもって経験してきたからです。
勉強が伸び悩むのは才能ではなく、やり方が間違っているだけです。
でも、テクニック的に勉強して、テストの点数や合格だけとっても、将来に役に立ちません。
でも、本質的な考えに基づいて勉強すれば、テストも劇的に伸び、将来にも応用が効きます。
正しく勉強できれば、成績は伸び、受験も合格でき、何よりも将来に活きるんです。
逆に、正しく勉強できなければ、がんばっても結果が出ず、「才能がない」と思い込んでしまいます。
勉強は才能ではなく、やり方の問題です。正しくやれば、誰でも面白いほど伸びます。
無料講座では「正しい勉強法」について、体系的に深くまでご紹介しています。お子様の成績アップのために、ぜひご活用ください。
今なら、登録いただいた方へ
を無料プレゼント中です!
多くの生徒の成績を上げたノウハウがギュッと凝縮されているマニュアルのため、ぜひお受け取りください!